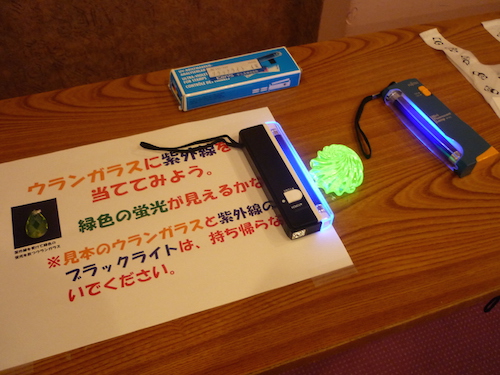~新たな視点による小・中・高校カリキュラムの創出~
| 開催日時 | 平成27年2月14日(土)13:00〜16:40 | |
|---|---|---|
| 会場 |
ホテルチューリッヒ東方2001 エーデルワイス 〒732-0052 広島県広島市東区光町2丁目7-31 |
|
| 内容 | 13:00~13:05 | 開会行事・開会挨拶 |
| 13:05~13:15 |
趣旨説明「エネルギー教育の新しい視点」 講師:関西福祉大学発達教育学部准教授 金沢緑先生 |
|
| 13:15~13:50 |
情報提供「高レベル放射性廃棄物の現状と課題」 講師:NUMO |
|
| 13:50~15:10 | 授業実践事例発表 | |
| 15:30~16:15 | グループ・セッション 授業実践に向けての話し合い | |
| 16:15~16:35 | 発表とディスカッション | |
| 16:35~16:40 | 閉会行事・閉会挨拶 | |
ワークショップ 当日の様子
平成27年2月14日(土)、広島県広島市のホテルチューリッヒ東方2001において「エネルギー環境教育教職員セミナー ~新たな視点による小・中・高校カリキュラムの創出~」が開催されました。広島大学エネルギー環境教育研究会と中国地域エネルギー環境教育研究会による共同主催の研修会です。
開会にあたり、中国地域エネルギー環境教育研究会の会長で広島大学名誉教授の田中春彦先生より「将来を担う子供たちにとって小学校・中学校・高等学校のカリキュラムを考えるということで、廃棄物問題の新しい視点を取り入れてのカリキュラム検討は意義があると思います。研究会で知識を深めていただき、活発な議論をしていただきたい」とご挨拶がありました。
次に、セミナーの進行を務める関西福祉大学発達教育学部准教授の金沢緑先生からセミナーの趣旨説明とともに、エネルギー環境教育を考える上での発達段階に添った内容の系統性とカリキュラムの系統性に関する解説がありました。
また、NUMOから、「高レベル放射性廃棄物の現状と課題」と題して、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業の概要に関する説明を行いました。
その後、研究会に所属されている先生方が現場で実践された内容の報告がありました。小学校中学年、小学校高学年の実践では、ゴミや廃棄物の問題をリサイクルの工程だけでなく消費や運輸の家庭も含めて社会的に考える授業の様子が紹介されました。
中学校では、理科の「科学技術と人間」の単元の中で日本のエネルギー資源の特徴や様々な発電方法の長所・短所を考えるだけでなく、放射性廃棄物の問題を教えた上で、日本の原子力発電の是非を議論する実践が報告されました。
高等学校では、物理の授業の中で核燃料や核分裂生成物の放射能について、半減期や崩壊定数をもとにした計算を通して科学的知識を習得する授業の中で、生徒が科学的根拠に基づいて社会的問題を考えようとする視点を得た実践の様子が報告されました。
その後、グループに分かれて実践報告をもとに、放射性廃棄物をテーマとした授業実践の可能性や、教材についての考え方、そしてカリキュラムにおけるエネルギー教育の系統性について議論しました。
最後に、広島大学エネルギー環境教育研究会の代表で、広島大学大学院教育学研究科教授の蔦岡孝則先生から「エネルギー環境問題は避けては通れない問題です。教育に携わる我々としてどのように社会に広げつつ、教室の中で子供たちに考えさせるのかを、先生方と考える機会として、研究会を開催していきましょう」とのご挨拶があって、研究会は終了しました。

広島大学名誉教授 田中春彦先生

NUMOからの説明