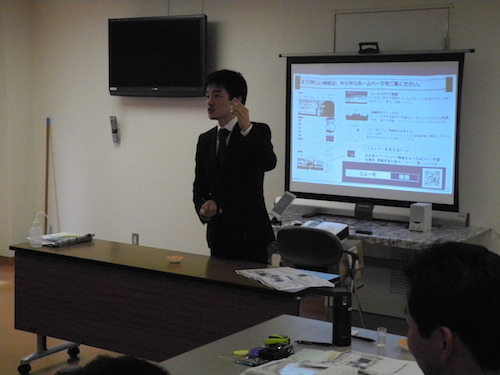~沖縄のエネルギーの今と未来を考えるワークショップ~
| 開催日時 | 平成27年2月22日(日)10:00〜15:00 | |
|---|---|---|
| 会場 |
琉球大学 研修者交流施設・50周年記念館 〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原1 |
|
| 内容 | 10:00~10:10 | 開会挨拶 |
| 10:10~11:00 |
講演 「エネルギー環境問題〜将来に向けて今考えること〜」 講師:エコット政策研究センター代表 中岡章 氏 |
|
| 11:15~12:10 |
情報提供「高レベル放射性廃棄物の現状と課題」 講師:NUMO |
|
| 13:00~14:10 | 授業実践事例発表 | |
| 14:15~15:00 | グループ・セッション 授業実践に向けての話し合い | |
ワークショップ 当日の様子
平成27年2月22日(日)、沖縄県中頭郡の琉球大学、研修者交流施設・50周年記念館にて「エネルギー環境教育セミナー~沖縄のエネルギーの今と未来を考えるワークショップ~」が開催されました。ご応募いただいた、沖縄地区の教職員の方々や大学生の方々にご参加いただきました。
冒頭、琉球大学教育学部の清水氏より、「本日はNUMOのワークショップ沖縄ということで今日は沖縄のエネルギーの今と未来を考えます。これまでの3回の研究会の中で小中校の授業開発、また中学で実践まで行って頂いたところがあります。午後にその報告があります。その報告を受けて、3月にある全国研修会に向けてブラッシュアップしていきましょう。」とご挨拶がありました。
次にNUMOから高レベル放射性廃棄物の処分事業が100年と長期に及ぶため、次世代の方々に知っていただくことが重要なこと、従って教育の観点で、子どもたちへのエネルギー全般の問題から最終処分の理解をして頂く機会が課題となることを開催趣旨として説明いたしました。
その後、エコット政策研究センターの中岡氏より「エネルギー環境問題~将来に向けて今考えること〜」というテーマで講演が行われました。エネルギー環境問題の概要や日本、世界のエネルギー政策、発電方法ごとの特徴などの説明がありました。
続いて、NUMOより「高レベル放射性廃棄物がどれぐらいあるのか」「高レベル放射性廃棄物の処分方法」「地層処分の特徴」「地層処分事業の概要」「教育事業への取り組み」について、情報提供を行いました。また、緩衝材に使用されるベントナイトの性質についての実験を紹介しました。
授業開発及び実践報告では、小学校、中学校、高等学校それぞれの教材開発および授業実践の報告がありました。
小学校の発表では「おきなわ電気エネルギーマップ」という教材について説明がありました。この教材は沖縄にある特色のある発電所に実際に足を運んで取材し、まとめたものです。実感を伴ったエネルギー教育をしたいとの想いから作られました。
中学校の発表では「沖縄の未来のエネルギー」をテーマに実際に行った授業の報告がなされました。この授業では知識構成型ジグソー法という手法を使い、沖縄の地理的特色、再生可能エネルギー、経済性の3つ焦点を当て沖縄の未来のエネルギーについて考えました。
高等学校の発表では「身近なエネルギー問題から地球環境への影響について考える」ということをテーマに3年に渡る工業高校の実践の報告がありました。この授業は理科、社会科、さらに生徒会と連携を行った学習です。1年目は「様々な地球環境からエネルギー問題について考える」2年目は「クリーンエネルギーによる発電とその有用性について考える」と3年目は「バイオマスエネルギーの研究」というテーマで行われました。今後も環境教育の重要性を認識し、工業高校としてものづくりや実験を通して授業を続けていきたいとのことでした。
それぞれの報告後に、報告を踏まえてディスカッションがなされました。

琉球大学教育学部 清水氏
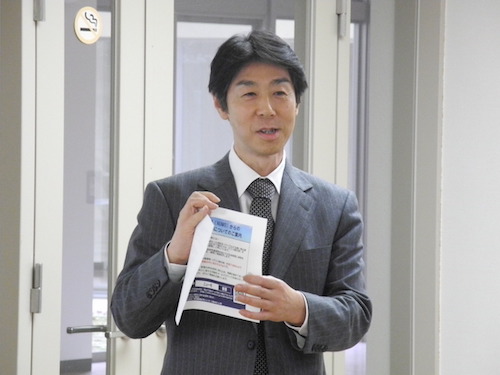
NUMOからの説明

エコット政策研究センター 中岡氏
ディスカッションで出された意見(抜粋)
○教師の実体験の話しはとても効果的。単なる写真、映像、インターネットの情報を見ても、一方的な受け手になってしまい、共感がない。教師がその場にいる写真などがあると、共感が生まれ、教材として非常に有効的なものになる。
○子どもたちに原子力に関する関心をもたせるのはなかなか難しい。そこで原子力発電所がある地域の子どもたちとテレビ会議システムをつかって、エネルギーに関して意見交換するという取り組みはいいのではないかと思った。
○意外に身近にあるものについて詳しく知らない。私たちが食べているものはどこから来ているのかなど。そう考えると、原子力発電所が沖縄にないから興味がないという以前に、何で電気ができているかがわかっていない。こちらから情報を提供して興味を持たせることが必要だと思った。