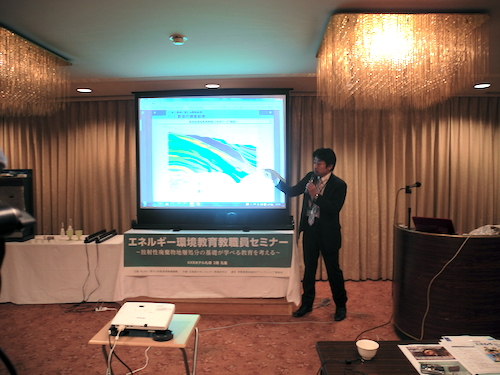エネルギー環境教育教職員セミナー(北海道)
~放射性廃棄物地層処分の基礎が学べる教育を考える~
| 開催日時 | 平成26年1月25日 (土) 13:00〜16:25 | |
|---|---|---|
| 会場 |
KKRホテル札幌 2階 孔雀 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西5丁目 |
|
| 内容 | 13:00~13:05 | 開会挨拶 |
| 13:05~13:35 |
オリエンテーション 「廃棄物処理を考えるために知らなければならないこと」 |
|
| 13:40~14:05 | 講義「エネルギー教育のカリキュラムについて」 | |
| 14:05~14:35 |
授業のオリエンテーション 「地層処分を考えるための素地を育てるために」 |
|
| 14:45~15:25 |
NUMOへの質疑と回答 |
|
| 15:25~16:00 | グループ討議 | |
| 16:00~16:20 | 発表 | |
| 16:20~16:25 | 講評 | |
ワークショップ 当日の様子
平成26年1月25日(土)、北海道札幌市のKKRホテル札幌において「エネルギー環境教育教員セミナー 〜放射性廃棄物地層処分の基礎が学べる教育を考える〜」が開催されました。ご応募いただいた、北海道地区の教職員の方々にご参加いただきました。
冒頭、北海道大学エネルギー教育研究会 幹事 平田氏より、「エネルギー環境教育の枠組みをどのように捉えているか。また我々の考える放射性廃棄物授業も学習指導要領の持続発展教育の枠組みで考えていきたい。学校教育の中でどこまで可能なのかみんなで知恵を出して考えていきたい。」とご挨拶がありました。また、NUMOからは、「原子力発電所の恩恵を受けてきた我々には放射性廃棄物を処理する責任がある。地層処分事業は広く国民に知ってもらうために、次世代を担う子どもたちにも知っていただきたいことである。そこで、学校の授業の中で取り上げていただけたらと思う。」と開催趣旨説明がありました。
その後、北海道大学名誉教授 杉山憲一郎氏より「廃棄物処理を考える為に知らなければならないこと」というテーマで講義が行われました。地層処分を教育現場で扱う材料として、恐竜の「化石」に注目した教材が提示されました。義務教育の関連する学習単元で化石ができる原理を学ぶことができれば、高レベル放射性廃棄物処分の科学的基礎が例解できるのではということをお話いただき、子供たちの興味のポイントに合わせ何ができるかを考えていくことが重要であるというお話がされました。
また、北海道大学エネルギー教育研究会の中学校グループによる講義と、授業づくりのためのオリエンテーションが行われました。放射線に関する知識や「地層処分を考えるための素地を育てるために」というテーマの具体的な学習指導案の紹介、その指導案の背景についての説明がありました。
続いて、NUMOより「地層処分事業の種類と処分方法」「高レベル放射性廃棄物とは?」「地層処分について」「地層処分の考え方」「合意形成に向けた取り組み」「学校教育について」という内容で、情報提供が行われました。この内容は札幌市内の教員による質問を元に作られており、その場にいる教員の皆さんが知りたい情報が提供されました。その際、緩衝材に使用されるベントナイトの性質についての実験やウランガラスの発光の様子を見る実験が行われました。また、参加者からの質問にNUMO職員が回答しました。
その後グループ討議が行われ、活発な議論がなされました。参加者の皆さんは5グループに分かれ、議論を行いました。

北海道大学 杉山名誉教授

NUMOからの説明
グループ討議で出された意見(抜粋)
○情報科学という部分で、科学的なことの知識とかの安全性をわかっているなかで、やはり自分事になった時にどうするのかというあたりを、教材であつかって、この処分場について知識を元に判断させていきたい。
○自分のために、未来の為に、国のために考えていかねばならない。そのためにはまずしっかりとした事実をおさえておくことが大事だというような姿勢をいろいろな科目でそういう姿勢能力、意欲を育てていくことが大事ではないのか。
○内容としては小学校段階で、内容の方は扱うには難しいところがある。ではどう小学校で素地を作って中高へつなげていくかっていうのが問題。
◯小学校の段階からいろんな知識をつけていくというよりかは考え方、それから皆で違った意見を持ったりしながらひとつの方向に導いていくというような経験をということが話しの中心だったと思います。
◯遮蔽の実験、地層処分のモデル実験ということでやってみました。これは価値がある実験で、これであれば中学3年生の発展学習で扱えそうだなという手応えを手にしたところです。